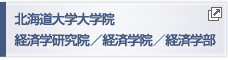金 仁子 協力研究員

- プロフィール
- 1997年(韓国)仁荷大学経営学部卒業。2018年北海道大学大学院経済学研究科博士後期課程修了。博士(経済学)。2018年4月~2020年3月北海道大学大学院経済学研究院専門研究員。2020年4月~2022年3月北海道大学大学院経済学研究院助教。
- 主要業績
- 「韓国における『貧困の女性化』」『季刊経済理論』54(1), 61-74, 2017。「日韓比較からみる男性の育児休業取得状況―パパ・クオータ導入を中心に」『經濟學研究』70(2), 111-123, 2020。
人々が担うべき日々の役割・責任の配分と,その社会的な評価とに関わる問題をジェンダーエクイティの観点から研究しています。
山本 崇史 協力研究員

- プロフィール
- 2002年弘前大学教育学部小学校教員養成課程卒業,2011年北海道大学大学院経済学研究科博士後期課程修了,博士(経済学)。2011年4月~2012年3月北海道大学大学院経済学研究科専門研究員。2012年4月~2014年3月北海道大学大学院経済学研究科助教。
- 主要業績
- 「初期ピグーの保護関税批判と厚生経済学の三命題」『経済学史研究』50(2), 2009年。「ピグー貿易論におけるマーシャル理論の継承と応用―『財政の研究』に即して―」『経済学史研究』59(1),2017年。
経済学史,特に英国の経済学史を主に研究しています。また,最近では,様々な経済学者を議論に巻き込んだ貿易政策論争の歴史に関心があります。過去の学説を考察し,そこから現代の地域に関する経済問題を解決するための示唆を得るような研究を,本研究センターで進めていきたいと思います。